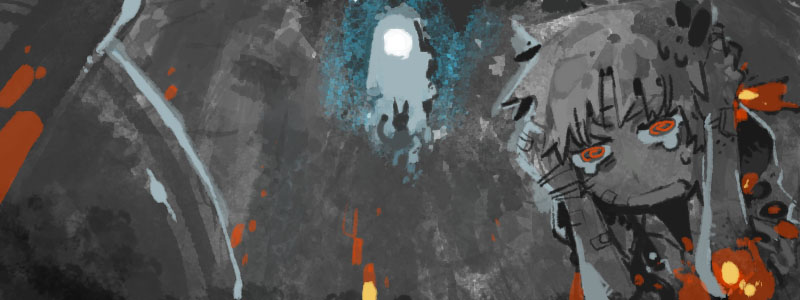
|
「参ったなぁもう…」 鍛冶屋の青年シック・ブレイムスは泣きそうになってぼやいた。こんな時刻にこんな場所でへたれこむことになろうとは夢にも思わない。ちなみにここは化粧室で、今は真夜中だった。 必要以上に頑丈なのだ。錠は自分が持ってきたので、そんなことは誰より良く知っている。あぁ、そうだ。戸の立て付けにも随分、張り切った覚えがある。「任せてください!」と薄い胸を叩いたりもした。蝶番なんかは最悪なことに一番良い出来の物を使った……あぁ、今では何もかも裏目だ。 化粧室の壁にもたれて両手で顔を覆い、採光窓から漏れ入ってくる月明かりに絶望する。換気口から進入する冷気に至っては、酒気の抜け切っていない彼の心身を蝕んだ。ここから猫 ――多分雑貨屋のおばあさんの飼っているあの―― が工具入れを引き摺り落としてしまったのが運の尽きなのだ。もう、どう頑張っても届きそうにない。手が届かないものなんて人生に一つだけで充分だと言うのに。 日暮れどきのことである。フロンティアパブの化粧室で最近どうも扉の立て付けが悪いということだったが、遂にひどく傾いて閉まらなくなってしまったのだ。まず居候のウェッソンがテムズに言われて扉の具合を確かめたが、蝶番が錆びて使いものにならなくなっており、トイレが使えないというのは酒を呑ませるパブにとっては由々しき事態だった。隣家に借りに行くというのにも限度がある。そこで当然の事ながら、偶然居合わせた鍛冶屋の自分は修理を名乗り出た。飛ぶようにして工場に戻り、道具を小脇に抱えてとんぼ返りで化粧室に走りこんだものだ。扉の修理は難なくこなしたが、パブの化粧室には簡単な錠しか備わっていなかったのが以前から気がかりだったので、好い機会だと取り付け作業に従事した。それが七時頃。重々しい柱時計の音を聞いたから確かだ。 ところが店ではウェッソンを筆頭に馴染みの医師やら近所の老爺やら、何でも屋の店主やらが集まって酒を呑みながらカードに興じ始めていたらしく、やがてぽつぽつと人が抜け、人数が足りないということで、鍛冶屋も強制的に引き込まれてしまった。面白いくらい負けに負けて眉の引き攣ったウェッソンに長丁場を付き合い、たらふく酒を呑まされて、それから……そうだ、途中で上手く抜け出して赤ら顔でなんとか作業に戻り、覚束ない手先を動かしていて、そして悲劇が起こった。押せども引けども内側から扉が開かなくなったのだ。閂(かんぬき)を使わない新型の錠の構造が複雑で、材料を作る立場で門外漢の彼にはやや持て余すものだったことは心得ていたのだが、妙に高揚した気分でそれを選んだのが良くない。にこにこしてテムズに見せ付けたのが今となっては遠い過去のように思われる。自分の二本の腕で取り付けたものなので特に慌てはしなかったが、工具箱を猫に取られてからは大いに慌てた。バールの一本もあればそれで片が付くのだが、もう手の出しようがない。図に乗って専門外のことにしゃしゃり出たが…由来、鍛冶屋というのは火がなければ何もできないのだ。自分はそういう存在だった。 結局、簡単な話で、あれこれいじった挙句に自分を閉じ込める完璧な檻を作ってしまったのだ。その時点でまず夜の十時は越えていただろう。悪いことに、化粧室の扉が修理中だということを知っていたからか、誰もここにはやって来ようとしない。外では庭木に不吉な夜風が騒ぎ始めていた。 前代未聞の大馬鹿者である。このまま朝が来れば全てが終わりだ。もし最初にここを訪れるのが彼女だったなら、もう…………………この街を出よう。それしかない。無駄に時間があるとそんなことにまで想い入ってしまう。 早く無難にウェッソンさん辺りがやって来ないだろうか…。まったくあの人は一体何をしているんだ。いつもほっつき歩いて、ろくに仕事もせずにやたら事件に巻き込まれてテムズさんに迷惑をかけて! こんなときに限って役に立たないのだ。いつも彼女の傍にいるくせに。そう、いつも彼女の傍にいるウェッソンが妬ましいのだ。そんなことは分かっている。 頭を抱えてすすり泣いていると、硬く閉ざされた戸の向こうから誰かの足音が聞こえてきた。鍛冶屋は慌てて、戸に耳をつけてみた。この足音は…間違いない、天使の君だ! どうして分かったのか、敢えて言うなら愛の力といったところか。いや、流石にそれは恥ずかしい。一人で照れているうちに、彼女はどんどん近づいてくる。シックは慌てて戸の隙間から………………って、隙間がない! なんて完璧な設計だ。これじゃあ天使が見えないじゃないか! この神経をすり減らせたときに彼女の姿を一目でも見ることが出来れば、どれだけ勇気付けられることかと思うのに…………。 ドアを叩いて自分の存在を知らせようかと腕を振り上げたが、それは力無くしな垂れた。こんな格好悪い姿を彼女に見せられるだろうか? 「ちょっと自分で取り付けた錠が開かなくなってトイレに数時間閉じ込められちゃって…あはは」「そう、大変だったわねブレイムスさん。今お茶を淹れるから…ぷっ」―――――あぁ。 ダメだ、何かが間違っている! 音がしないように両手で床を打って鍛冶屋はおいおいと泣き崩れるのだった。 「…さ、殺人事件ですぅ!!!!!」 という幾分快気の混じった黄色い声が脳天にぐりぐりと突き刺さり、目を白黒させて彼はやっと眼を覚ました。目の前に立っているのはこの近隣では幾らか有名なあの迷探偵だ。何故かいつもの丸眼鏡はなく、鼻先をくっつけるくらいに顔を寄せ、まるで死体を検分するようにして 「なんだ生きていたんですねぇ…」 こちらの様子を確かめると急にやぼったい眼になり、はぁ、と溜息をつく。 「まぁ、いいですぅ。それで犯人の顔は見たんですかぁ?」 「え、いや…」 誰にやられたんだろう? 敢えて言うなら睡魔か。間の悪さか。至らぬ自分自身にか。眠っていただけだった。彼は瞼の辺りを油に汚れた手の甲で擦った。扉が開かないのはまるっきり錯覚で、工具箱は何事もなくそこにあったし、仕事はとっくに終わっていた。どうして扉が開かないなどというおかしな幻想に身を包まれていたのだろうか。何故そんな情けない夢を見なければならないのか、思うと胸がむかついてくるのだが、誰が悪いわけでもない。 「サリー、どうしたの!」 テムズの声が聞こえたので鍛冶屋は床に手を突いたり、それを滑らせてこけそうになったりしながら、ようやく半腰まで身を持ち直して背筋を伸ばした。彼女は奥から姿を現すと艶っぽく――少なくとも彼にはそう見える―― 細い目つきで、「あら」と指を額に撫で付けてから「ブレイムスさん、もしかして…」と続けた。 「徹夜で作業してくれてたの? ごめんなさい、私…そうとは知らずに一人だけ寝ちゃってて……ありがとう」 寝巻きのスカートを挟むように屈み、大きく見開いた瞳のテムズに手をとられて、鍛冶屋はもう天高く舞い上がってしまいそうな心地だった。火照り、全身が沸き立つ。なんだかもう、そんな苦労などものともしない。あなたに喜んでもらえるためなら三日でも四日でも立てこもって見せます! あぁいや貴女が望むなら真っ赤に燃え盛る炉の中にだって飛び込みます! 本気でそう思っているが、口に出せるかどうかは……それはまぁ、なんと言うかつまり別問題なのだが、とにかくごにょごにょと口元を動かすしかできない。乾いた口の中に僅かに滲み出た生唾を無理やりに呑む真似をした。そこで彼は急に、半ばテムズの手を振り払うようにして立ち上がった。怯えているのだ、こんな間抜けな自分が彼女に嘲笑されはしないかと。 彼女は僅かに戸惑ったようだった直ぐに気を取り直した。 「助かりました。本当にありがとうブレイムスさん。今お茶を淹れるから」 「………………」 そして彼女は――――――決して自分を見て吹き出したりなどはしなかった。そうだ、この人はいつだって自分の気持ちには真摯に応えてくれるじゃないか。 (そうか、だから僕はこの人が好きなんだ―――――) 悪夢はもうすっかり覚めていた。俯きながら、彼女を好きになって良かったと心の底から思った。それだけで姫君の手を取る騎士のような、誇らしい気分にさえなった。もし誰かが炉の中に飛び込もうとしていたら、他の人間が呆然と立ち尽くしても、彼女は間違いなく高く叫んでその愚か者を止めようとするだろう。根拠はないが、彼女は必ずそうする。そういう情熱のような魅力を、出逢ったときから強く感じていた。正義感とか慈愛とか、そんなに難しいものではない。自分の彼女への思いも、同じくそんなに難しいものではない。 その瞬間、なんだか決心していた。落とした視線のまま自分の掌を広げて見る。火傷ばかりで斑に赤黒く、鎚を握るそれはごつごつと不細工な岩肌のようだ。自分の長所と言えば、多少、人より小手が利くだけだというのに。馴染みの先生のように医療で人を救えるわけじゃないし、ウェッソンさんのように銃の心得もなくて、誰かを暴力から守れるわけでもない。だからと言って、洒落た詩の一つも作れやしない。美男子なわけでもないし、貯金だってささやかだ。技術や知識も仕込んでくれた親方に比べればまだまだ大したことはない。 だけど、だけど自分は誰よりも彼女の魅力を知っている。今はそれでいい。一つ一つ、未熟な部分を情熱で叩き直していけばいい。これまでもそうしてきたように。彼女の前にどんな悪漢が現れても絶対に逃げないで立ちはだかってみせるし、彼女が困っているなら全力で万策を尽くすと誓う。だから、 (もっと笑顔にしてみせるさ) そのためにはまず自分が笑顔でいることだ。誰が絶望に打ちひしがれても、自分は彼女を支えなければいけない。彼女の前でだけは、情けない顔なんかするもんか。 後ろから今頃ウェッソンがやってきて、サリーと何やら他愛のない口論をしている。鍛冶屋はさっきまでとは少し違う気恥ずかしさで、テムズに背中を向けて工具の片づけを始めた。 「もうお暇しますから…」 「まだ冷えるもの。身体を温めていった方がいいわ」 しかしテムズがそう提案したので、断る理由もなかった。自分の部屋に向かおうとしていた他の二人も頷いて着いて来る。歩きながら、とても不思議な心地だった。 「殺人事件って一体なんだったんだ?」 「気にしなくてもいいわ、いつものことよ」 その家族のような近しさが、羨ましい。彼はいつか自分もそれを別の形で手に入れたいと、二人の背中を追いながら思った。いつも跳ね回っているサリーはくたびれた服に、三つ網を垂らして欠伸しながらよたよたと最後尾だ。 「気をつけてサリーちゃん」 覚束ない足取りで躓きそうな少女の手を取ると。 「あ、すみませんブレイムスさん」 年若い店主が母親のようなことを言う。そんなに恐縮することはないのだ。自分はそんなにも、貴女にとって遠い存在ですか? 他人ですか? そう尋ねたくなる。そんなことは無論、恐ろしくてできない。だが確かめなくとも、手を伸ばせば届く距離に彼女がいて、話しかければ答えてくれる。それが嬉しい。今はそれだけでいい。その距離をほんの少しずつでも縮めていければいつの間にか温もりを得ることができるのではないか…いや、温もりを与えることができるのではないか。不思議と、自分にはそれができる気がした。 女の顔はことによれば百にも千にもなるが、男の顔はただ二つ。仕事をしているときと、していないときのものだ。友人のガンマンなどは「ほぅ」と息を漏らしたものだったが、彼女はまだそれを見たことがなかった。だからきっと思い出とも言えないほどの思い出として、しかし胸の内に、小さくても芯の通った何かを残しただろう。その瞬間の彼の眼差しと言えば職人らしい手つきで鉄床(かなとこ)を撫でるときのそれに至極、似通っていた。仕事を始める前に決まってする所作で、彼が束の間、鉄の強さと焔の情熱を得るときでもある。 だから炎のような紅い髪を波打たせて振り返ったとき、彼女が思いがけず驚きの声を上げたのも無理はない。初めて逸らさず、その瞳に見つめられたのだから。 「ブレイムスさん……そ、その、紅茶でいいかしら?」 「ええ。お願いします…あ、テムズさん」 「え?」 明日にも消えてしまうだろうその勇気にさえ―――― 「ありがとう」 今は微笑む。 由来、火さえあれば鍛冶屋に出来ないことはない。 |